|
ID-S55 運転中の転がり軸受の異常を見つける方法は 用途によっては、転がり軸受の運転中、絶対に故障を起こしてはならないものがあります。そのような用途に対して、運転中の転がり軸受の異常の有無を見つける方法には、どのようなものがあるのでしょう。 一般に、機械が使われ始めてから寿命になるまでの故障の発生率は、図1に示すようなバスタブ(浴槽形)曲線になるといわれています。 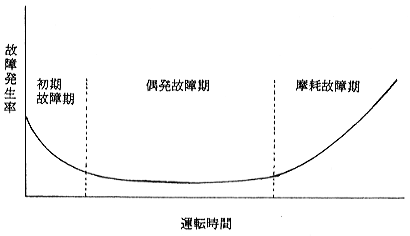 図1 機械の故障発生率 始めの段階でおこる初期故障は、転がり軸受の場合、その使用条件に応じた軸受の選定、潤滑・密封、軸とハウジングの設計・製作、取扱い、取付けを適切に行えば、皆無にすることができます。 次いで、偶発故障の期間を経て、摩耗故障すなわち寿命になります。 転がり軸受の寿命には、材料の転がり疲れに起因するフレーキング寿命と潤滑劣化による表面の摩耗に原因がある機能寿命の2つの種類があります。 これらの寿命に至る前に、その兆候を出来るだけ早く予知する方法が、いろいろと研究・開発されています。 ●機械を保全するには 装置工業における設備保全のために、予防保全(PM=Preventive Maintenance)方式があります。PMには、ある一定期間ごとに補修を行う時間基準保全(TBM=Time Based Maintenance)と設備診断技術によって設備の劣化や故障の有無を観測し、必要な時期に必要な保全を施す状態基準保全(CBM=Condition Based Maintenance)の2つの方法があります1)。 そして、CBMで定期的あるいは常時行うのが診断すなわちモニタリングです。 ●転がり軸受の異常をモニタリングするには 転がり軸受に発生するいろいろな異常現象と、それを検出するために、現在、一般に使われている方法の有効性を検討して、表1に示しました2)。 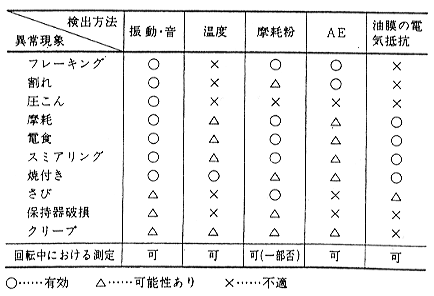 (振動と音響)軸受が振動する結果として音響が発生します。現場では、回りの騒音が大きいために音響の測定が困難なことが多いので、実用例としては振動測定が多いです。表1をみても、振動法はいろいろの種類の異常に対して有効です。 (温度)温度は手軽に測定することができるので、よく使われます。しかし、いろいろな異常現象をひろく検出するのには向いていません。使用限界温度のある軸受材料や潤滑剤に対するチェックまた軸受の取付けミスによる異常の発見には有効です。 (摩耗粉の分析)潤滑剤中の中に混入した摩耗粉を分析して軸受の状態を調べることができます。摩耗粉は微細で少量なので、高度な分析技術と高価な分析装置が必要になります。 現在使われているのは、SOAP(Spectrometric Oil Analysis Program)法、フェログラフィ法および磁性プラグ法が代表的なものです。軸受の異常と摩耗粉の形状、質、量の間の関係を診断するには熟練が必要です。 (AE)アコースティック・エミッションは、材料内部の微視的構造や組織の変化に伴って発生する弾性波といわれ、一般に数10KHz以上の超音波領域の周波数成分を持ちます。AE法は異常が材料内部に発生した段階で捕らえることができるので、早期予知の可能性をもっています。 しかし、現状ではAEの発生機構の解明が不十分であるために判定がむづかしいことと、AE信号のエネルギーが微弱で、外乱ノイズの影響を受け易いなどの問題点があります。 (油膜電気抵抗)内輪軌道−転動体−外輪軌道との間に形成される潤滑油膜の電気抵抗を測定して、潤滑状態から軸受の異常を診断します。この方法は、測定のためのハウジングの絶縁と回転軸からの電気信号の取出しなど、実用上の困難があります。 ●なぜ振動法がよく使われているのか 振動法は、表1に示した軸受の異常の多くを検出することができます。また、図2に示すように、10数μm程度の小さな傷を見つけ出すことができることと、傷の大きさとの相関が良いことなどです2)。 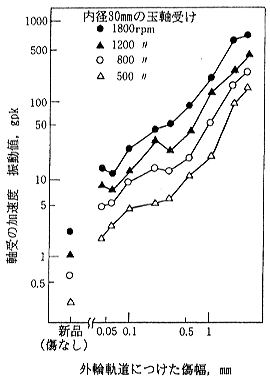 図2 外輪軌道につけた傷幅と軸受の加速度振動値 振動法による転がり軸受の異常検出には、一般に1K〜15KHz程度の周波数範囲の加速度が使われます。 ●異常はどのようにして見つけるのか 軸受の振動波形を時間に対して記録すると、図3のようになります2)。 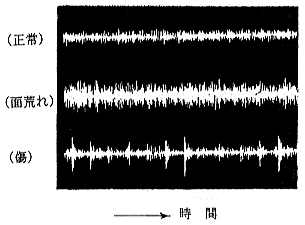 図3 軸受の振動波形 新品の“正常”な軸受でも、振動波形は時間に対して交番的に、しかもランダム(不規則)な変化を示しています。 (実効値)潤滑剤が劣化して潤滑状態が悪くなり、内外輪の軌道や転動体の表面が摩耗して粗さが大きくなると、図3の“面荒れ”のように、正常より大きいレベルのランダムな波形になります。この状態を定量的に表わすには、波高の2乗平均値である実効値(rms値)が使われます。実効値は表面の荒れによる劣化の程度と相関がよいので、異常判定の基本量になります。 (ピーク値)しかし、軌道や転動面にフレーキングや傷が発生し、図3の“傷”のように規則的なパルス状の波形になると、実効値では検出能力が劣り、パルスの尖頭値を示すピーク値が正確な指示になります。ピーク値はフレーキングの初期の段階の検出能力に優れています。 (波高率)振動波形のピーク値の実効値に対する比率を波高率(クレスト・ファクタ)といいます。転がり軸受での実験によると、正常な軸受振動の波高率は4〜5であるのに対し、フレーキングが発生すると波高率は10以上になることがあります2)。 波高率は、軸受の大きさ、運転条件また振動の測定条件が変わっても、フレーキング発生を即時診断できる判定基準として有効です。しかし、面荒れの検出には向いていません。 (エンベロープ分析)傷やフレーキングによるパルス状の振動波形を周波数分析することによって、軸受の中の内輪、外輪、転動体のどの場所に損傷がおこったのかを推定することができます。 傷の発生位置によって、発生する衝撃振動の発生間隔周波数は、表2に示すように軸受の内部諸元から計算で求めることができます2)。 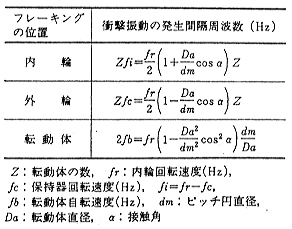 このため、振動波形信号のエンベロープ分析(包絡線検波分析)を行うと、パルス発生の間隔周波数をよく検出できるようになります。 ●上述のような振動波形の信号処理プログラムのすべてを組み込んだ、転がり軸受専用の異常予知または異常診断機が実用化され、すでにフィールドで多数活躍しています。 |
「参考文献」
| ||||
|
「出典」 | ||||
Copyright 1999-2003 Japan Lubricating Oil Society. All Rights Reserved.