|
ID-S61-2 ボールねじにはどのような特徴があるのか 送りねじの相対運動する面に、ボールの転がり運動を使ったのがボールねじである。ボールねじにはどのような特徴があるのか? 回転運動を直線運動に変える機械要素として送りねじがある。その“おねじ”の山と“めねじ”の谷の間に玉をいれて、ねじ面の滑り接触運動を転がり接触運動に変えたのがボールねじである。 ボールねじの考えは、古くは1874年の米国特許、1879年のドイツ特許にみられる。1909年の英国特許には、今日使われているボールねじと殆ど同じ構造の図がみられる。 ●実用化は自動車のハンドルから ボールねじが実用になったのは、第2次世界大戦(1939〜1945年)で使われた航空機といわれている。そして、1955年米国GM社の自動車で、ハンドルによって前輪を動かすステアリング・ギアに使われたボールねじが、量産としては始めてのものである。この機構のためのボールねじは、1958年日本では日本精工で始めて生産された。 さらに、1965年頃から、日本の数値制御(NC)工作機械の送り機構に、ファナック社のNC制御装置と組合わされて、NSKの精密ボールねじが使われるようになった。それが、今日のNC工作機械の世界的な全盛時代を創り出すのに大きな役割をはたした1)。 ●ボールねじにも色々な種類が ボールねじの玉が進む速度は、ねじ溝の軌道が進む速度の1/2になるので、玉はナットの後側から排出されてしまう。そこで、この玉をナット前側のねじ溝に戻して、ナットのねじ溝の中を玉が無限に循環する構造が必要になる。その構造には、図1のように、チューブ式、こま式、エンド・キャップ式の3種類がある。 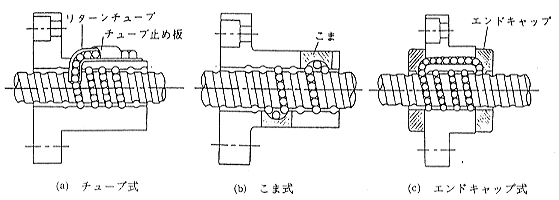 図1 玉をナットの中で循環運動させるナットの構造 現在、チューブ式がコスト・パフォーマンスが良いので最も普及している。こま式はナット外径が小さくでき、エンド・キャップ式は大リード用に使われている。 ねじとナットの溝形状には、図2のように、円弧形状とゴシック・アーク形状のものがある。後者はねじとナットの溝と玉との間のすきまを小さくしても、玉と溝との間の接触角(普通は45°)を大きくすることができるので、ナットのアキシアル剛性を大きくできる特長がある。 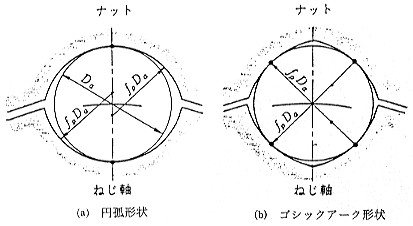 図2 ねじとナットの溝形状 ●ボールねじを使うと 送りねじにボールねじを使うと、滑りねじに比べて次のような利点がでる。 ・ねじ軸を回転駆動するトルクを1/3以下にすることができる。従って、ボールねじを駆動するサーボ・モータの小形・軽量化ができる。 ・起動摩擦トルクと運動摩擦トルクの差が小さく、またスティック・スリップがおこらないので、メカトロニクスにとって制御性の良いメカになる。 ・ナットを2個使うか、または予め大きな直径の玉を使うかによってナットに予圧をすることができる。従って、ナットのすきまを殺し、さらに剛性が高められる。これもメカトロニクスにとって、制御性の良いメカになる。 ・高い送り精度を容易に実現することができる。 ・ボールねじの摩耗寿命と転がり疲れ寿命は計算によって予測できるので、運転の信頼性を高められる。 ・寸法も精度も国際的に標準化され、専用工場で量産されているので、使い易く、コスト・パフォーマンスが良い。 ●摩擦が小さく、効率は高い 図3に、ボールねじのリード角、摩擦係数、効率の間の関係を示した。 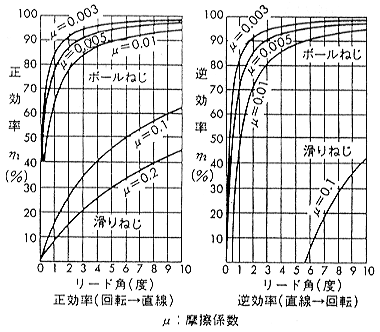 図3 ネジのリード角−摩擦係数−効率の関係 ねじとナットの間の接触面における摩擦係数μは、滑りねじでμ=0.1〜0.2程度であるのに対して、ボールねじではμ=0.002〜0.004程度になる。従って、ねじまたはナットの一方にトルクを加え、それによって他方のナットまたはねじに発生した軸力が仕事をするときの効率は高く、90%を超える。 そのため、ねじまたはナットの直線運動をナットまたはねじの回転運動を変える、いわゆる逆作動も容易にできるという特徴もあらわれる。 ●送りの精度は ねじ軸が1回転したときに、ナットが軸方向に進む距離をリードと呼ぶ。ボールねじの精度では、このリード精度が重要である。JISでは、累積リードの基準値Tに対して、図4のような4つのリード精度を規定している。 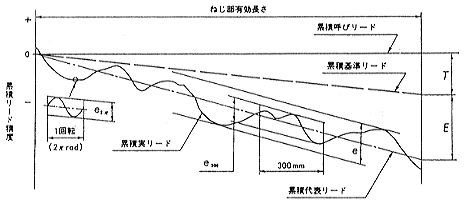 図4 ボールねじの精度
現在、規格化されている最も良いリード誤差の許容値を表1に示した。ボールねじが高精度化すると、ボールねじ自身の精度だけでなく、ボールねじを取付ける周辺の部品の精度とその組立精度は、少なくともボールねじと同等またはそれ以上であることが必要となってくる。
●高速化は ボールねじを使って、高速送りすることができる。その場合、リードの大きいボールねじを選び、ねじ軸の曲げ1次固有振動数の80%以下の回転速度で使うことが必要である。 ボールねじの許容回転速度n(rpm)は、ボールの中心を通るピッチ円直径をdm(mm)とすると、精度等級C7以上の精密ねじで、dmn≦70,000、特に高速化に対する考慮をすれば、dmn≦150,000が可能になっている2)。 ボールねじの高速化に伴う発熱による温度上昇を低減させるためには、中空ねじ軸を使って冷却液を強制的に貫通させる方法がある。また、ねじ軸の温度上昇による送り精度の変化を減少させるために、ねじ軸に予張力を加え、温度の影響を変位で吸収する方法も使われている2)。 | ||||||||||||||||||||
「参考文献」
| ||||
|
「出典」 | ||||
Copyright 1999-2003 Japan Lubricating Oil Society. All Rights Reserved.